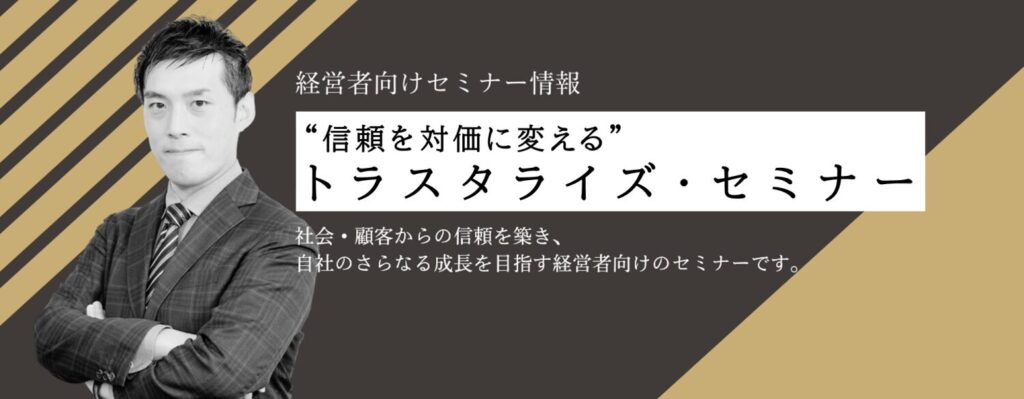第70回 不祥事で失墜した信頼を取り戻す「仕組み」――信頼の再生に必要な5つの原則
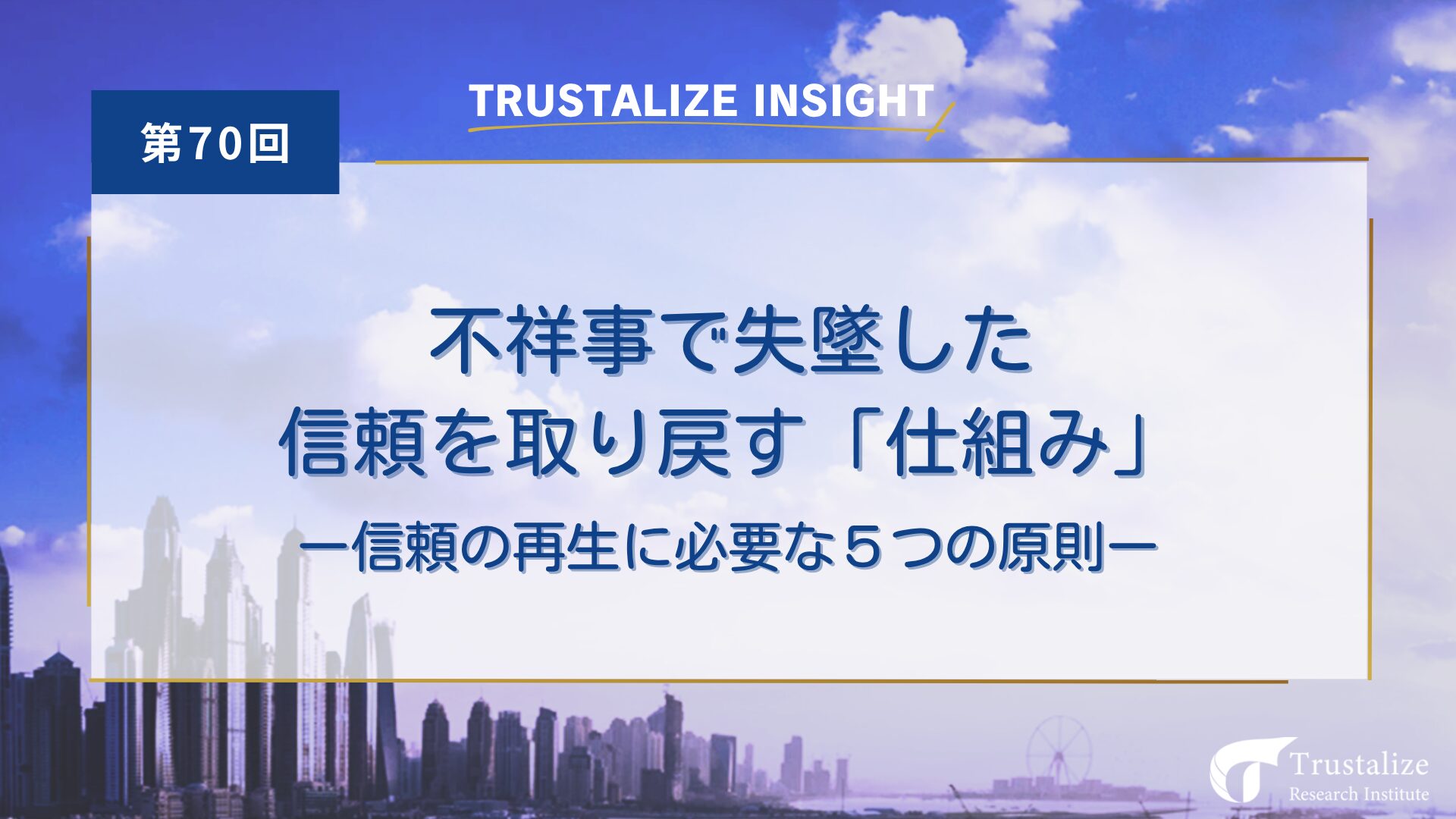
「売上が減ることより嫌なのは、社員の家族から“あの会社、大丈夫なの?”と思われることなんですよね…」
先日、ある経営者がこんな胸の内を明かしてくれました。地方のとある中小企業で、数年前に比較的大きな回収騒ぎを起こしてしまい、信頼を大きく損ねてしまった会社の2代目社長です。
信頼は、目には見えませんし決算書にも載りません。
けれど、取引先や社員の心の中に着実に積み上がり、企業の将来価値をかたちづくる資産です。不祥事によって“信頼残高”がゼロを切れば、商材の工夫や価格の割引程度では埋めきれない大きな損失を背負うことになります。
過去にご紹介した第50回では、不祥事直後の「初動対応」――すなわちスピード、責任、情報開示の重要性に焦点を当てました。今回はその続きとして、宣言した改善策を「やり切る」ための経営管理に視点を移します。
信頼を再生するための5つの原則
「謝ったら終わり」では信頼を取り戻すことはできません。必要なのは、“約束したことを実行する力”です。もし信頼喪失の当事者となってしまった場合、再生のために意識すべき原則は次の5つに集約されます。
1. 透明性は「継続性」で測られる
危機直後の情報開示の透明性は、多くの企業が意識するところです。しかし問題となるのは、その後の進捗共有が時間とともに薄れていくこと。
透明性をきちんと評価してもらうには、単発の開示だけでなく、「継続的な発信習慣」が重要になります。改善状況の確認・外部への報告の仕方を定期的に確認し、「いつ・誰が・何を」伝えるかを計画・実行していくことが必要です。
2. 謝罪だけでなく「被害者の救済」も重視する
ひとたび不祥事が起こると、社内の動揺や説明責任に気を取られがちですが、最も先に見るべきは被害者の救済です。どれだけ誠実な発言をしても、「行動が伴っていない」と感じられれば、むしろ信頼は遠のきます。
まずは補償、安全確保、影響範囲の把握といった「具体的な回復」を最優先に。
そしてそれをKGIやKPIとして明確に管理し、進捗が誰の目にも見えるようにする。
被害者の安心とその可視化が、信頼再生の第一歩になります。
3.短期利益から、「信頼指標」中心のOSに入れ替える
不祥事が起きる背景として、短期の利益や効率を優先しすぎる社内の“空気”があるケースは少なくありません。この空気=組織のOSを変えない限り、再発防止策は「その場しのぎ」にとどまります。
経営においても、単なる収益指標だけでなく、「信頼」形成に関わる行動や成果を指標化し、意思決定に組み込むことが必要です。
たとえば、「顧客満足度指数」や「クレーム処理の平均日数」など、具体的に想起しやすいものをKPIとして設定し、定期的にレビューしながら、“信頼を測る習慣”を経営の基本姿勢に据えることが、体質の転換をもたらします。
4. “拒否権”を持つ外部を活用する
組織の内側からでは、どうしても見えない死角があります。
とくに信頼が喪失した後は、「内部だけで完結した反省」はむしろ危険です。
そこで重要なのが、“客観的視点で指摘し、時には耳の痛いことも言ってくれる外部の存在”を、経営のなかに入れること。
たとえば、社外取締役や第三者委員会、信頼ある取引先や金融機関など。
彼らに「方針を変える力=拒否権」を持ってもらうぐらいの覚悟が、組織の視野を外に開き、信頼再生の本気度を示すうえで効果を発揮します。
5. 過去ではなく、「未来像」を物語と数字で示す
信頼を失った直後の会社の説明は、どうしても過去の説明や責任の取り方に終始しがちです。しかし、信頼回復に向けては「これからどう変わるか」を社内外に示すことも不可欠です。
その際、必要なのは物語と数字の両方です。方向性の説明だけでなく、いつまでに何をどれだけ実行するか、どんな姿を目指すのか。それらを中期目標などの形で明文化し、実行サイクルに乗せて具体的に行動していくことが、再出発の土台となります。
ケーススタディ|Galaxy Note 7──失った信頼をどう再設計したか
少し前の話ですが、2016年、SamsungはGalaxy Note 7のバッテリー発火問題により、全世界で約300万台の自主回収に踏み切りました。ニュースなどでも大きく取り上げられたので、記憶にある方もいらっしゃるでしょう。このときのSamsungの損失は53億ドル、ブランド価値は一時6%以上落ち込んだとされ、過去最大級の危機であったといえると思います。
ですがSamsungは、まさに先ほどの5つの原則を、経営のしくみとして実装することで再起を果たしました。
具体的には、
- 継続的な情報開示として、事故原因や再発防止策を複数回にわたって公式発表・説明会・ウェブサイト等で段階的に公開。技術面では、20万台以上の端末を分解する徹底調査を行い、その分析結果も含めて社会と共有した。
- 被害者中心の対応として、返金・交換対応に加え、通信キャリアへの手数料もSamsung側が負担
- 組織のOS刷新として、“8ポイント・バッテリー安全検査”を導入し、品質KPIを取締役会で毎月レビュー
- 外部の声の取り込みとして、Battery Advisory Groupを設置し、技術監査を外部と共に実施
- 未来像の提示として、Note 8で安全設計の哲学を打ち出し、さらに社会的課題への対応として環境方針・CO₂削減などの目標を公表
こうした再設計の結果、翌年には世界スマートフォン市場でシェア1位に返り咲き、その後のブランドイメージもV字回復を果たしています。
中小企業でもできる、信頼の再設計3ステップ
「そうはいっても、Samsungのような大企業だからできたんでしょう?」
といった声も聞こえてきそうですが、中小企業にも実践できる示唆もあります。
- “信頼KPI”を2~3つ決める
例:クレーム是正完了率、対応日数、顧客満足アンケート回収率など。まずは「測る」ことから始めてみる。 - 週次・月次・四半期でレビューを回す
定期的に実施することに加え、現場→経営会議→金融機関や支援者などの第三者へと、視点を広げてチェックを重ねていく。 - あえて“NO”を言ってくれる存在を持つ
社外顧問、取引先、金融機関、顧客代表など――
「ちょっと、本当にそれでいいの?」と言ってくれる人を、仕組みの中に巻き込む。
内部のみで完結することによる視点のずれを防ぐには、こうした“うるさい味方”を持つことが有効。
不祥事は、会社のなかで明るみに出ていなかった闇の部分に、突然スポットライトが当たるようなものです。そこにどう向き合い、会社のあり方をどう再設計するか――そこに、理念と成果の両立を目指す経営者の胆力が問われます。
- 透明性を継続する
- 被害者に本気で向き合う
- OSを入れ替える
- 外部の目を入れる
- 未来像を具体的に示す
これらの原則に基づき、業務の仕組みを一新できたとき、失った信頼を再び蓄積し、いずれは事業を支える資本に変えるためのサイクルが動き出すのです。
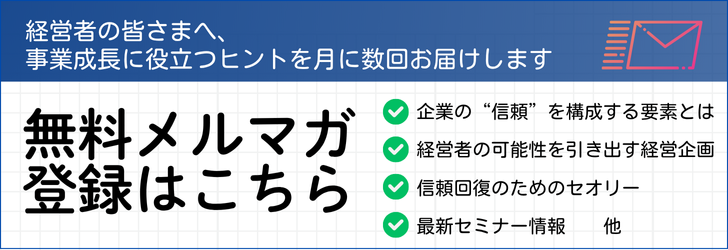
著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

最新刊
企業の信頼を対価に変えて収益性を大きく高める「トラスタライズ」5大ポイント
自社が大切にしてきた「信頼」や、潜在的な無形の価値を、どうすれば大きな対価に変えて収益をあげていくことができるか…。
信頼を対価に変える独自メソッド「トラスタライズ」の手法で企業のこれまでになかった収益の上げ方を提示する専門家が、その具体的なポイントを社長の視点で解説した実用書。

目次
ポイント1:「対価に変えられる信頼」の見つけ方
ポイント2:信頼を効率的に対価に変える戦略の描き方
ポイント3:信頼を可視化・証明する仕組みの作り方
ポイント4:信頼から確実に対価を得るための訴求のやり方
ポイント5:信頼活用に向けた社内の意識改革のやり方
価 格:¥2,200 (税込)
発売元:日本コンサルティング推進機構