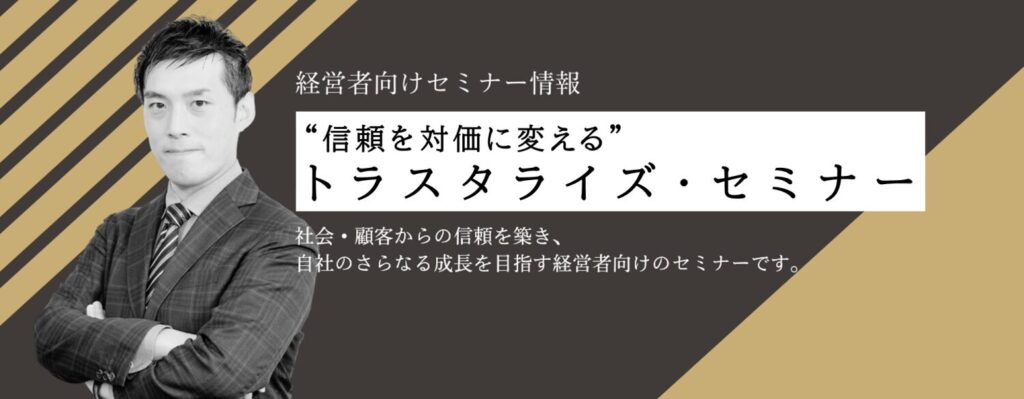第71回 事業承継の時こそ考えたい「経営計画」の活用
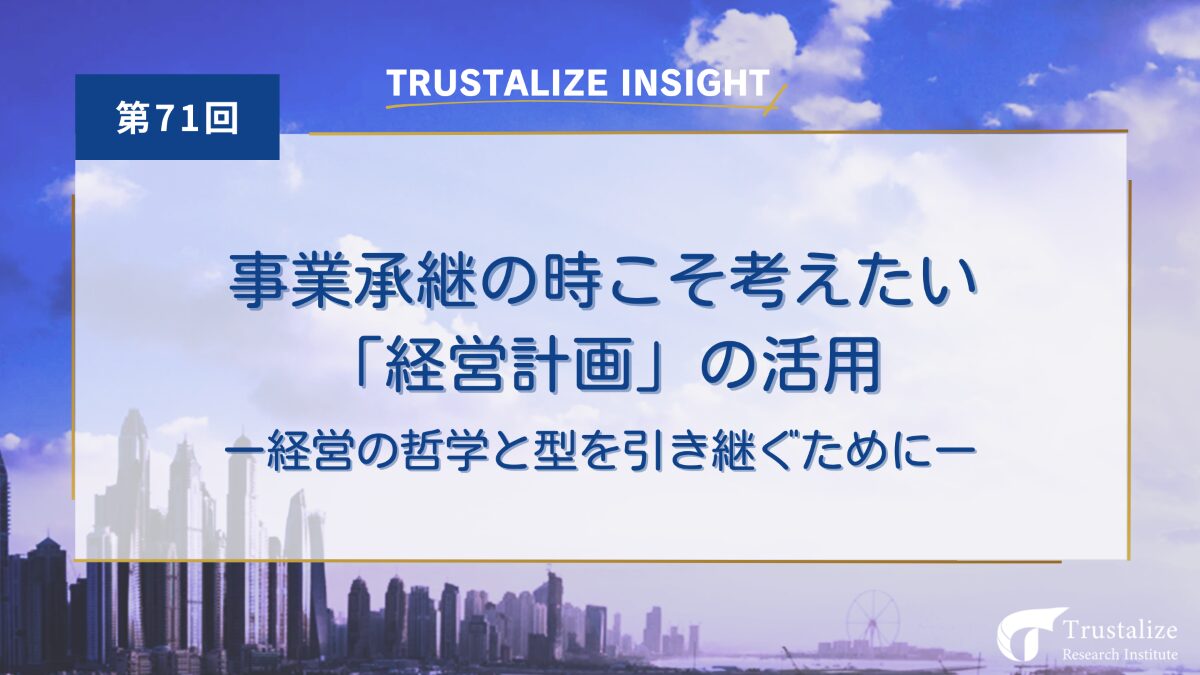
社長とその後継者が議論を重ねながら経営計画を策定することは、その検討プロセスも含めて、円滑な事業承継の助けになります。
先日、かつて中期経営計画の策定をご一緒した社長と再会する機会がありました。その方は、3か年計画のスタートと同時にお父様から事業を引き継ぎ、社長に就任された後継経営者です。
「あの時池尻さんと一緒に計画を作り、運用の仕方も考えて頂いたおかげで、何とか一人立ちできていると思います」
そんなありがたいお言葉を頂き、とてもうれしくなりました。当時この社長とともに色々と悩んだことが、今では承継後の経営を支える礎になっていると実感できたからです。
経営計画は社長の「哲学」と「型」を引き継ぐ器
事業承継というと、どうしても「事業そのものの引き継ぎ」に目が向きがちです。けれども実際には、先代が培ってきた経営哲学や意思決定のスタイルといった「見えない資産」も引き継がなければ、事業の軸は次第に揺らいでしまいます。
経営計画は、事業承継を円滑に進めるための有効なツールです。計画の策定過程で先代と議論を重ねれば、売上や利益の目標だけでなく、「なぜこの方向を目指すのか」「何を自社は大切にすべきなのか」といった価値観や判断基準も自然と共有されます。さらに、計画をどう運用するか――たとえば「どの頻度で振り返るのか」「修正が必要な場合は誰がどの手続きを踏むのか」といったルールを明確にしておけば、経営の「型」そのものを承継できます。
特に承継前後が親子関係である場合、会社の中ではそれぞれに役職があり、あえて他人のようにふるまうことも少なくありません。親子関係をもちこまないという意味では有効なのですが、それゆえに経営について改まって話す機会が少なくなってしまうケースが意外と少なくありません。そのような日常を離れ、事業承継に向けた親子の対話を促すきっかけとしても、過去と将来を見据えた経営計画づくりは有効です。
また、この効用は親族承継に限ったものではありません。M&Aや社内昇格による承継の場合でも、経営計画は「見えない哲学」と「経営の型」を受け渡す重要な器となります。血縁や長年の関係性がない場合にも、経営計画を通じて価値観や方向性を共有することが、承継後の混乱を防ぎ、新しい体制への信頼を築くために不可欠です。
創業者と後継者の違いを意識した事業承継
創業者は、事業の隅々まで理解し、自ら判断してきたため、仕組みによる経営をあまり必要としなかったかもしれません。しかし後継者にとっては、その暗黙知を同じように再現するのは難しいものです。
だからこそ「目指す姿」「財務数値」「部門ごとの施策」「実行スケジュール」といった要素を、時間をかけてでも経営計画として可視化しておくことが、新社長の信頼構築に寄与し、承継成功の可能性を高めます。
例えば、目に見える形で経営計画を用意しておくことで、経験の浅い経営者であっても取引先や金融機関に対して自社の方向性を自信を持って説明できるようになります。これは承継直後にスムーズに信頼を形成するために大きな助けとなります。
また、計画の存在は従業員にとっても安心材料になります。新しい経営体制に移る中で「会社はどこへ向かうのか」という不安は少なからず生まれますが、計画があればそれを具体的に示し、組織全体に心機一転頑張っていこうというメッセージを伝えることができます。
外部の視点を取り入れる意義
日々の経営の傍ら、濃密な議論をしながら中期経営計画をつくろうとすると、3か月から半年ほどの期間を要します。さらに、策定段階から社員などほかの人も巻き込もうとすれば、より長期のプロセスになることもあります。途中で頓挫することなくこのプロジェクトを形にするには、外部の専門家を起用することも選択肢の1つになるでしょう。
さらに、近年は事業環境の変化が激しく、社会的要請への配慮もより強く問われています。また、施策の網羅性や計画のわかりやすさを確保するためにも、第三者の目を取り入れることは一考に値します。専門家の知見を入れることで、承継後の経営がより実行可能で持続性のあるものへと磨かれていくでしょう。
外部支援は単なる「知識の補充」にとどまりません。アドバイスだけでなく社内の議論にも踏み込んで参加する専門家であれば、先代と後継者の対話を整理し、時には橋渡し役として機能することもあります。その結果、世代間で共有しづらい価値観や優先順位を言語化し、計画に反映できるのです。
事業承継において大切なのは、「事業」だけでなく「哲学」と「型」を次代につなぐことです。経営計画は、そのすべてを受け渡すための器となり、外部支援を組み合わせることでさらに確かなものになります。
承継のタイミングを「飛躍の第一歩」に変えるために、経営計画の活用と運用をあらためて考えてみてはいかがでしょうか。
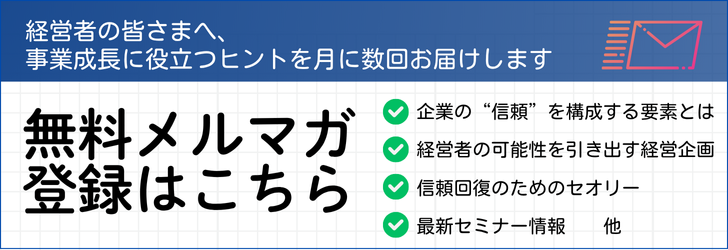
著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

最新刊
企業の信頼を対価に変えて収益性を大きく高める「トラスタライズ」5大ポイント
自社が大切にしてきた「信頼」や、潜在的な無形の価値を、どうすれば大きな対価に変えて収益をあげていくことができるか…。
信頼を対価に変える独自メソッド「トラスタライズ」の手法で企業のこれまでになかった収益の上げ方を提示する専門家が、その具体的なポイントを社長の視点で解説した実用書。

目次
ポイント1:「対価に変えられる信頼」の見つけ方
ポイント2:信頼を効率的に対価に変える戦略の描き方
ポイント3:信頼を可視化・証明する仕組みの作り方
ポイント4:信頼から確実に対価を得るための訴求のやり方
ポイント5:信頼活用に向けた社内の意識改革のやり方
価 格:¥2,200 (税込)
発売元:日本コンサルティング推進機構