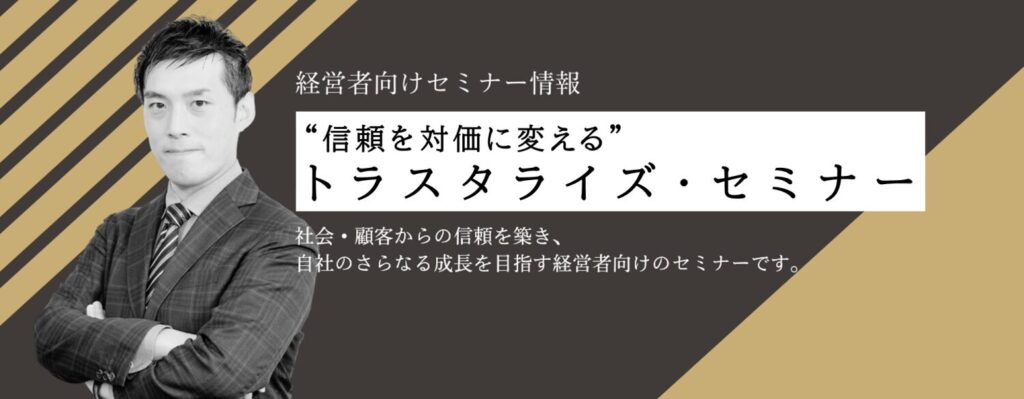第77回 事業承継時に、経営者の求心力をどうつくるか
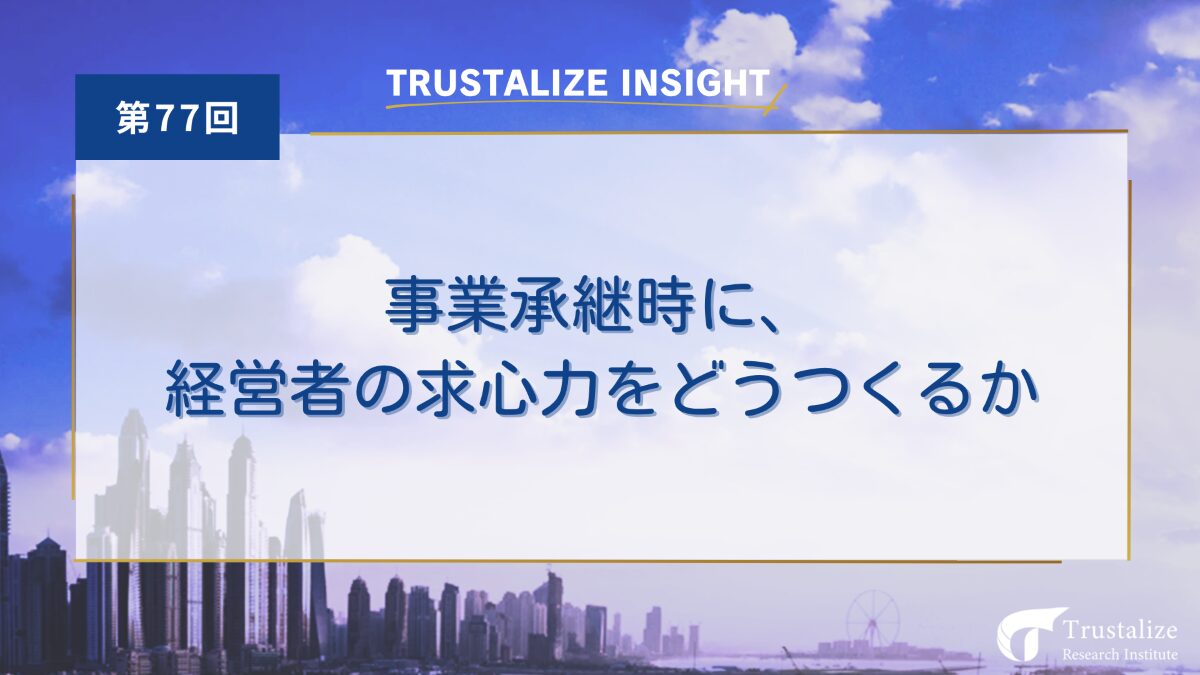
承継直後の経営者は、”正しく”未来を語ることで求心力と信頼獲得を加速させることができます。
「正直言うと、年齢も社歴も上の古参の社員たちが自分についてきてくれるのか、不安なんですよね・・・」
ある二世経営者の方が、承継を目前にして、このように打ち明けてくれました。
経営者としての実績を重ねていけば、自然とリーダーシップが備わっていくかもしれません。しかしそれには長い時間がかかります。一方、会社の舵を取るのは待ったなし。承継直後こそ、社員の心を一気に惹きつけるか、それとも見透かされてしまうか、分岐点となります。
では、その「求心力」をどうすれば短期間で形にできるのか。今回は、新しく就任する経営者が早期に社内で信頼を得るための方策を、3つの視点で考えてみたいと思います。
理想の未来像で人を動かす
「人はパンのみにて生くるにあらず」という言葉があります。社員は給料のためだけに働いているわけではありません。自分の仕事が社会にどう役立っているのかを感じられるかどうかで、会社への姿勢は大きく変わります。
承継直後の経営者はまだ実績で示せません。古参社員の目には「この若い社長に任せて大丈夫か」という不安が映っているでしょう。若手社員にも、これからの長い人生を委ねる可能性のある会社の経営がどうなっていくかは大きな問題です。だからこそ、まず必要なのはどんな未来に会社を導くのかを語ることです。
ここで大切なのは、数字だけの目標ではなく、社会的意義をも含めた将来像を語ることです。製造業なら「お客様の安全や安心を、見えないところで支える」、建設業なら「地域の暮らしを守り続ける」といった形です。社員が「誇れる会社だ」と思える方向性を本気で打ち出すことで、言葉に重みが宿ります。
そして、その未来像に至る「道筋」を示すことも欠かせません。完璧な計画でなくてもいいのです。「本気でそこを目指す」という熱意が伝われば、社員の心は動き始めます。承継のタイミングは、経営者としての最初の物語を描く最大の機会。気恥ずかしさもあるかもしれませんが、理念やビジョンを明確にし、何度も語り続けることを、求心力を築く第一歩として強く推奨しています。
日常の関わり方と組織運営
経営者の求心力は、日々の業務の中においても培われます。社員が「自分は組織のなかでこれからも大切にされるはず」と感じられるかどうかが、経営者交代後の初期の信頼を左右するケースが多いようです。承継直後の時期こそ、日常の小さな関わり方が大きな意味を持つのです。
具体例としては、人事評価やフィードバックが挙げられます。評価の内容そのものよりも、経営者が社員の仕事ぶりをよく見ており、気にかけているという事実が人を動かします。「あの案件、よくまとめたね」「日々の〇〇の努力は見ていますよ」と一言伝えるだけでも、社員の心に残ります。形式的な表彰もそうですが、日常的な言葉が圧倒的に効果を発揮します。
一方で、新しい社長が組織全体をどう動かすかも注視されています。たとえば会議の場です。社長が一方的に結論を押し付けるのではなく、社員の意見を聞いた上で意思決定を下す。そのプロセスに参加することで、社員は「自分たちが会社を動かしている」という感覚を得ます。そして最終的に社長が方向を示すことで、経営は社長個人のものから組織によるものに移り変わっていきます。その結果、「この人の下で進もう」という一体感が生まれる素地が生まれます。
日常の声かけと組織運営、この両輪が揃って初めて、社員は経営者を信じて動き始めます。承継直後は不安も誤解も生まれやすい時期ですが、だからこそ小さな積み重ねが求心力を大きく育てるのです。経営者自身が現場をよく見て、誠実に向き合う姿勢こそが、最も強いリーダーシップとなります。
節目を意図的に用いて社内の結束を強める
人の心は、日常の積み重ねだけでなく、非日常の体験によっても大きく動かされます。経営者の求心力を高めるためには、節目を「儀式」として演出することにも一定の効果があります。承継直後こそ、会社に新しい風を吹き込むチャンスなのです。
典型的なのは創業〇周年などの節目行事です。たとえば記念パーティーや社内表彰を行い、これまでの歴史を振り返ると同時に、新しい未来を打ち出す。その場で経営者が堂々とビジョンを語れば、普段は懐疑的な社員も「この人についていこう」と感じる瞬間が生まれます。もし特別な周年がなくても、年に一度の経営計画発表会や全社員集会を「会社の節目」として位置づければ、同じ効果を得られます。
儀式の力は「非日常を共有すること」にあります。普段は業務に追われている社員も、特別な場に身を置くことで気持ちをリセットしやすくなります。たとえば経営計画の発表会をホテルの会場で行い、最後に全員で記念写真を撮るだけでも、「自分はこの会社の一員だ」という実感が強まります。これは数字や資料だけでは決して得られない効果です。
経営者はこうした儀式を通じて「言葉を明文化し、約束し、確実に実行する」強い決意と姿勢を示すことができます。結果がどうであれ、誠実に向き合う姿勢を社員に見せる。それ自体が強い信頼につながり、次の一年をともに進む力になるのです。儀式は単なるイベントではなく、経営者の求心力を一段引き上げるための大切な装置になりうるのです。
事業承継の時期は、経営者にとって最大の試練であり、同時に最大のチャンスでもあります。中長期の経営計画を示し、日常で信頼を積み重ね、節目を儀式として演出する。この三つを意識することで、時間をかけずとも社員の心を惹きつけることは可能です。
もちろん、経営者ひとりの努力には限界があります。だからこそ経営計画や管理の仕組みを整え、「仕組みを通じて会社を動かす」ことが求心力を持続させる鍵となります。誠実に語り、約束し、実行する姿を重ねていくことで、承継の不安は次第に自信へと変わっていきます。未来をつくる力は、確実にあなたの手の中にあるのです。
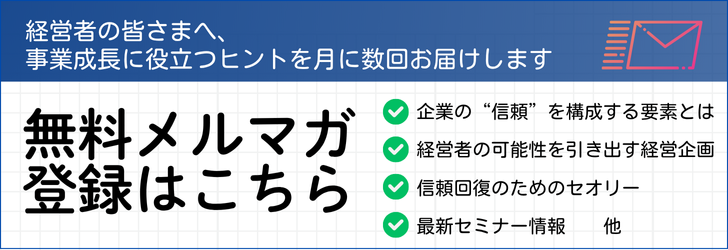
著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

最新刊
企業の信頼を対価に変えて収益性を大きく高める「トラスタライズ」5大ポイント
自社が大切にしてきた「信頼」や、潜在的な無形の価値を、どうすれば大きな対価に変えて収益をあげていくことができるか…。
信頼を対価に変える独自メソッド「トラスタライズ」の手法で企業のこれまでになかった収益の上げ方を提示する専門家が、その具体的なポイントを社長の視点で解説した実用書。

目次
ポイント1:「対価に変えられる信頼」の見つけ方
ポイント2:信頼を効率的に対価に変える戦略の描き方
ポイント3:信頼を可視化・証明する仕組みの作り方
ポイント4:信頼から確実に対価を得るための訴求のやり方
ポイント5:信頼活用に向けた社内の意識改革のやり方
価 格:¥2,200 (税込)
発売元:日本コンサルティング推進機構