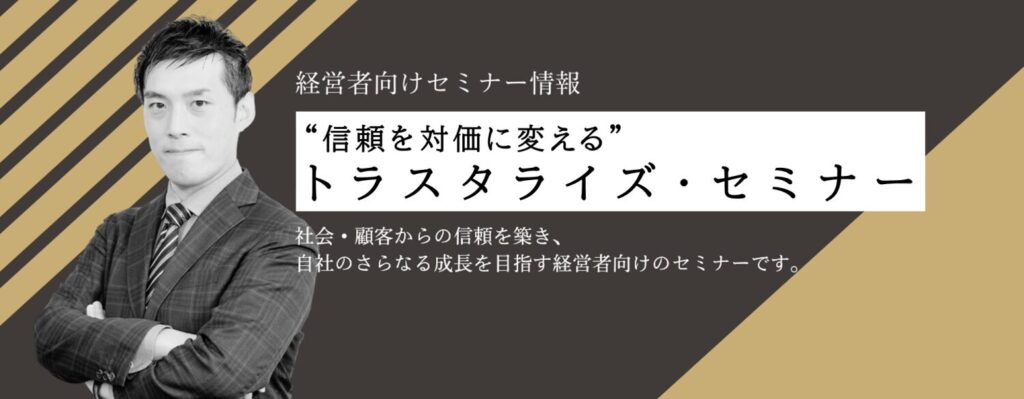第78回 中小企業の人材不足は“採用・雇用”では解決しない――外部人材の力を活かす経営術とは
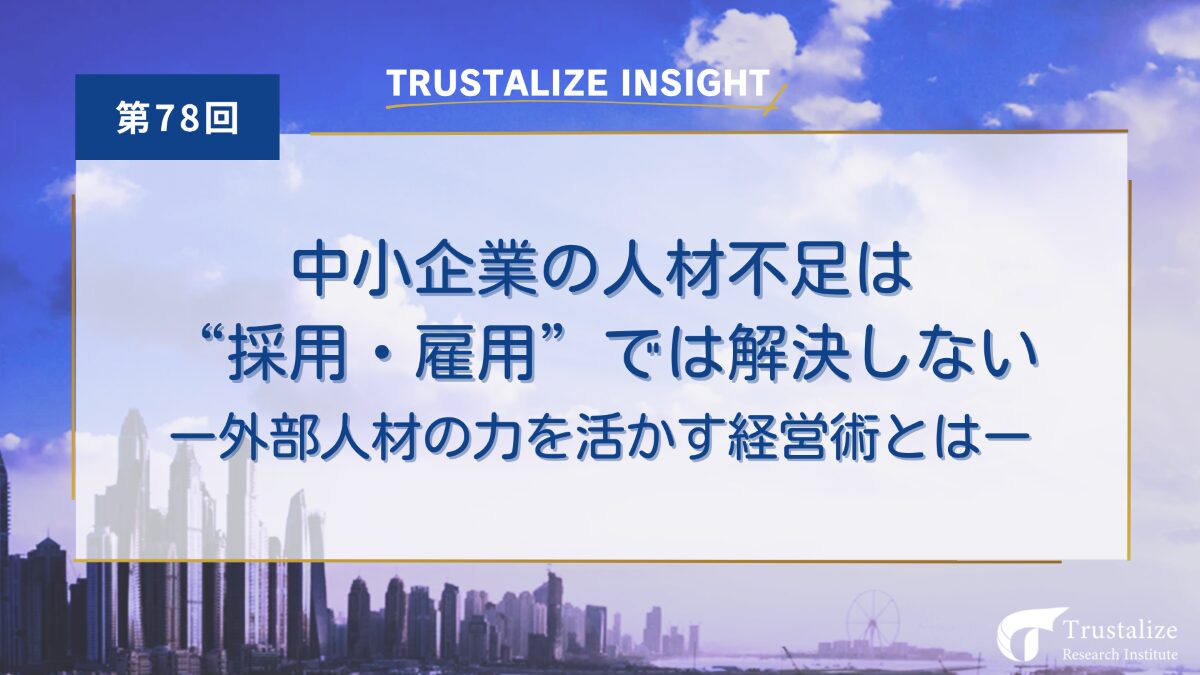
採用難が常態化するなか、中小企業は「雇用」だけでなく、信頼関係でつながる協業ネットワークとして経営を再構築する時代を迎えています
「求人頑張っているんですけど、なかなかいい人が来ないんですよね……」
経営者の方から、そうした声を聞くことが近年増えてきました。
少子高齢化という言葉が叫ばれて久しく、そもそもの働き手の数は減少しています。
それだけでなく、働き手の意識自体も大きく変わりつつあります。
努力や工夫では乗り越えられない“構造的な採用難”に直面している会社が増えるなか、今回は雇用以外の、より緩やかで自由度の高い人の活用のあり方について取り上げます。
雇用・人材活用の前提が変わった
一昔前まで、「会社に属する」ことは生活の安定の象徴でした。しかし今の働き手にとっては、それが必ずしも魅力あるものではなくなっています。自分なりのキャリアプランに基づいて専門性を高め、複数の仕事やプロジェクトに関わる。あるいは、生活の柔軟さや仕事以外の部分も含めて自己実現を優先する。そんな新しい価値観が、確実に広がっています。
「同じ会社で長く働く」ことが絶対的な価値ではなくなった今、企業もまた、かつての「採用して育てる」モデルを維持するのが難しくなっています。人件費の上昇、教育コストの増加、そして何より、辞めることが特別ではなくなった働き手の意識の変化。こうした流れを受けて、人を雇うこと自体がリスクを伴う時代になりつつあります。
つまり、企業と個人の関係性そのものが変わってきており、企業は雇用以外の選択肢にも目を向ける必要が出てきているのです。
“一緒に働く”のかたちが多様化する
実際にいま、現場では新しい関係の形が広がりつつあります。正社員にこだわらず、業務委託や副業という形で関わる個人。企業を横断して動く専門家、あるいは複数の会社を兼務するプロフェッショナル。かつては一部のクリエイティブ職やIT職に限られていたスタイルが、今では経理、広報、教育、営業支援など幅広い分野に広がっています。
こうした新しい仕事は、クラウドソーシングやマッチングサイト、紹介などを通じて生まれています。既に、大企業から中小企業まで、あらゆる規模の会社がこのような形での協業・発注に取り組んでいます。そしてこの流れを上手に取り入れる会社は、単に採用や雇用コストを下げるためではなく、必要に応じて柔軟に「専門性を借りる」仕組みを整え始めているといえるでしょう。これができれば、採用がすぐに上手く行かずとも乗り切れる場面も出てくるはずです。
不足しているのは“人手”ではなく、“知恵と経験”だと気づいた経営者ほど、個人の力を組み合わせて経営を強くしていく方向に舵を切っているのです。協業により足元の専門性を、採用と育成により長期の成長基盤を得る――そんな二層構造で経営を設計していく発想が求められています。
組織を閉じずに、広げる
個人の力を活かす経営には、実際の職務に応じて様々な形態がありますが、明確な共通点・注意点もあります。それは、「今までの組織運営のあり方だけでは対応しきれない」という点です。
必要なときに必要な専門性を取り入れることで、会社の枠を超えた“ゆるやかなチーム”が生まれます。そこには正社員・業務委託・パートナーといった多様な人材が混在しますが、当然、既存の価値観やルールだけでは対応しきれない部分も出てきます。目的や成果、役割分担、チームとしての約束事――これらを逐次明確にしながら進める、いわばプロジェクトマネジメント的な思考が不可欠になります。
また、こうした体制を運営するうえで重要になるのは、早期に信頼関係を構築することです。同じ組織に属していない人同士が連携して成果を出すためには、「この人となら信頼して一緒に働ける」という関係を築くことが何よりも大切だからです。
この信頼という観点で、経営者が特に気にされるのは、「外部の専門家は期待通りに働いてくれるだろうか」という点でしょう。しかし同時に、もしくはそれ以上に、「この会社は信頼できるパートナーだろうか」と相手から見た安心感をどう生み出すかという視点も欠かせません。
そのためには、社会への貢献を事業の根幹に据える、誠実でクリーンな取引を続けるといった姿勢を示して、優秀な働き手を惹きつける“信頼の証”をつくっていく取り組みが求められるでしょう。このような信頼構築の取り組みは、本コラムでも数多く取り上げているので、ぜひご参照頂ければと思います。
働き手が仕事に求める価値観は、ここ数年で大きく変わりました。筆者自身も、かつては1社に勤めていましたが、今は異なる形で複数の仕事に携わっています。最近登壇したイベントでも、新しい働き方を実践・検討している方々に多く集まって頂き、新たな働き方へのニーズを強く感じました。
採用・育成にとらわれない、より緩やかな働き手との協業は、今後さらに多くの企業で現実的な選択肢になっていくはずです。採用難という制約を逆手に取り、社内外の人々の得意を活かした経営体制を整えていく。組織を「固定された人員構成」としてではなく、信頼でつながるネットワークとして捉え直すことが、これからの中小企業の持続的成長には必要不可欠になっていくでしょう。
雇用ではなく協働。上下関係ではなく信頼関係。
当社も、経営の機能そのものを代行するサービスを展開し、経営者の方にとっての“外部リソース”として寄り添い続ける存在を目指していきます。
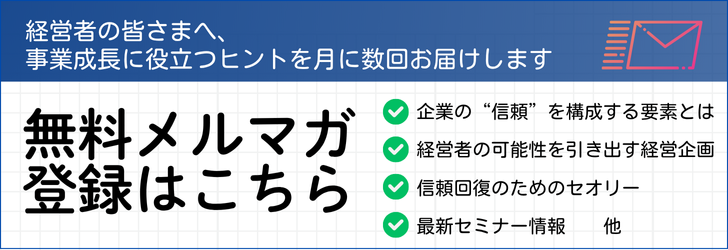
著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

最新刊
企業の信頼を対価に変えて収益性を大きく高める「トラスタライズ」5大ポイント
自社が大切にしてきた「信頼」や、潜在的な無形の価値を、どうすれば大きな対価に変えて収益をあげていくことができるか…。
信頼を対価に変える独自メソッド「トラスタライズ」の手法で企業のこれまでになかった収益の上げ方を提示する専門家が、その具体的なポイントを社長の視点で解説した実用書。

目次
ポイント1:「対価に変えられる信頼」の見つけ方
ポイント2:信頼を効率的に対価に変える戦略の描き方
ポイント3:信頼を可視化・証明する仕組みの作り方
ポイント4:信頼から確実に対価を得るための訴求のやり方
ポイント5:信頼活用に向けた社内の意識改革のやり方
価 格:¥2,200 (税込)
発売元:日本コンサルティング推進機構