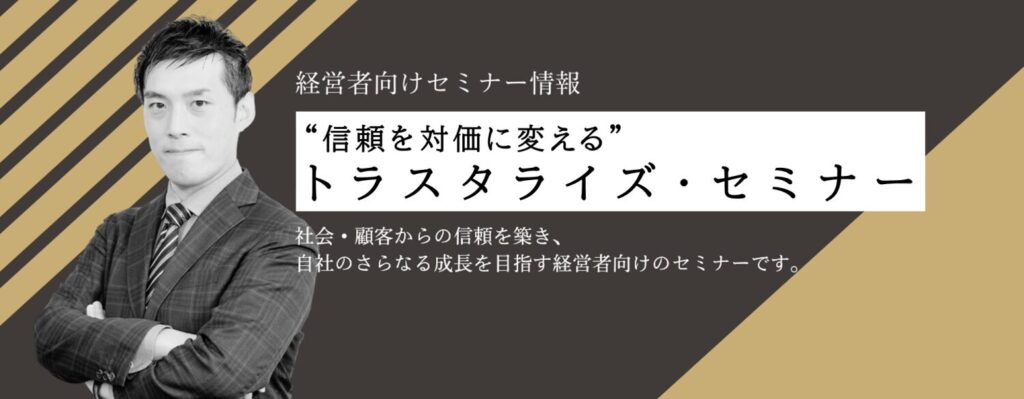第80回 事業承継した社長のための”現場訪問の心得”
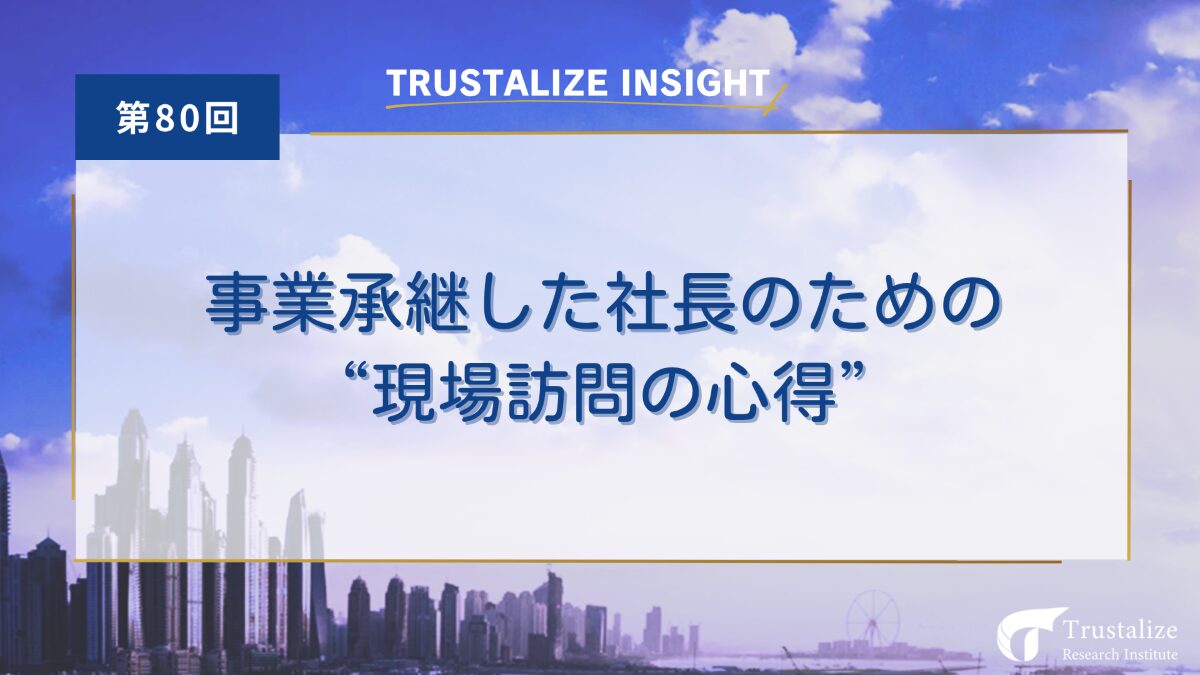
承継社長こそ、現場に足を運ぶべきときがあります。関心と経営をもって訪問することで、組織の信頼と判断の確かさが培われていきます。
「もっと現場に足を運ぶべきか、それとも担当部署に任せるべきか、迷っているんです」
最近事業承継をされたある社長が静かに話されました。
組織はある程度整っており、現場を預かるベテランの責任者も存在する。そんななか、自分がどこまで現場に出ていくべきか迷っているとのこと。
私はこう申し上げました。
「ぜひ行かれるのがよいと思います。ただし、”どう行くか”には注意してください。どういうことかというと・・・」
後日その社長は、現場の支援も兼ねて現場に入りました。実際に手を動かしながらスタッフに声をかけ、終わり際には日々のお礼を伝えたそうです。
その後、現場からは「来てくれたことが力になった。ありがたかった」との声。
たった一度、短時間の訪問でも、現場の空気がやわらいだのだといいます。
今回は、やった方がいいと思いながらもなかなか時間が取れない、そんな“社長の現場訪問”について取り上げます。
「任せる」と「無関心」は違う
「現場は任せているから」と言う経営者は多いものです。
けれど、任せることと無関心でいることは、似て非なるものです。
現場に足を運ぶことで得られるものは、数字では拾い切れない”実感”です。
お客様の動き、従業員の表情、空気の温度。
そうした細やかな情報が、経営の勘を磨きます。また、現場を見てきたという事実自体が、社長の発言にさらなる説得力を生みます。
そしてもうひとつ。社長が見に来てくれるという事実そのものが、現場にとって大きな励みにもなります。場合によっては緊張感という形で表れるかもしれません。いずれにせよ、「気にかけてられている」と感じることが、現場の日々の努力を支える一端となるのです。
それは、社長が何かを“指示する”以上の意味を持ちます。
訪問とは、現場への敬意の表明でもあるといえるでしょう。
ただし、訪問はあくまで“関心の示し方”であって、“過度な介入”は極力避けるべきです。見る、聴く、感謝を伝える——この3つを丁寧に行うことが、健全な距離感を保つ秘訣です。
現場訪問の作法——軽く、静かに、丁寧に
社長が現場へ行くとき、最も大切なのは「現場の時間を過度に奪わないこと」です。
いうまでもなく、多くの企業にとって現場は収益を生むための場所です。その現場に、「社長訪問対応」という業務を課すことは、社長自身が思う以上に負担となります。社長が現場から遠ざかっていればいるほど、社長が目にする”かもしれない”場所の整理整頓、社長から聞かれる”かもしれない”質疑応答への準備などに膨大な工数が割かれるからです。
現場訪問を大切にしつつ、現場の負担を必要以上に増やさないための心得をいくつかご紹介しましょう。
まず、”大名行列にしない”こと。
社長と共に、色々な役員や上級管理者が同行するというのはよく起こる話です。人数が増えれば増えるほど、受け入れる側は対応に頭を悩ませることになります。場合によってはそれぞれの送迎、席順決めなど、本来現場がすべき仕事とはかけ離れた業務に工数を割かれることになります。
これを避けるため、訪問の際には同行者を最小限にし、短時間で済ませること。
準備を求めれば求めるほど、現場に負荷がかかるだけではなく、その現場本来の姿も見えなくなっていきます。
次に、その場で指示をしないこと。
気づいたことは持ち帰り、関係部署を通して整理をさせる方がよいでしょう。社長の何気ない一言が、現場では重く響くからです。
そして、見たことすべてを真実だと思わないこと。
状況にもよりますが、訪問の直前に現場は整えられ、普段と違う動きをすることもあります。
見た目の印象で判断せず、一呼吸おいて「この光景の裏には何があるか」にも思いを巡らせる。そうした姿勢が、真の観察につながるはずです。
最後に、忘れてはならないのは感謝を言葉にすること。
「ありがとう」「いつも助かっています」の一言で、人の表情は変わります。これは単なる礼儀ではなく、組織を前に進めるエネルギーに変わります。
現場のことを慮る姿勢と行動が、社長本人の信頼にもつながっていくのです。
現場を経営に活かす——PDCAに“現場”を取り込む
承継社長にとって、現場に行くこと自体が目的であってはいけません。
大切なのは、そこで得た気づきを経営の改善サイクルに生かすことです。
多くの場合、事業承継した社長に求められるのは、チームや仕組みを活用した経営です。創業者と比べ、事業や組織に対する理解や発言力が乏しいのが一般的であるため、いわば民主的に経営を進めていく必要があります。
そんななかで求められるのは、経営の計画を立て、PDCAを回していくという考え方です。この時、社長自らが現場訪問することは、特に”C(Check)”の段階で重要な意味を持ちます。
経営を進める社長の目線からいえば、机の上で数値を検証するだけでは、どうしても限界があります。そこに現場での確認、つまり「現地現物」の視点が加わると、PDCAの精度は格段に上がります。
たとえば、
「数字上は順調でも、実際には従業員が疲弊している」
「改善策を打ったはずが、お客様には伝わっていない」
といったズレは、現場に立たなければ見えてきません。
現場で感じた違和感や小さな変化を“仮説の材料”として持ち帰り、部署の責任者と一緒に確かめ、次のAction→Planへと反映する。この循環が早まるほど、経営判断は確かになり、組織は強くなります。
現場の目線から見ても、社長が訪問することで、経営の方針や計画が何であり、現場がすべきことは何であったかを振り返る要因にもなります。日々の業務に忙殺されるなか、全社の方針や計画に目を向けることは疎かになりがちです。そんなときに社長が訪問することは、現場側にとっても実態を知ってもらいつつ、自分たちの業務や行動を見直すきっかけにもなりえるのです。
社長の現場訪問には、数字では測れない力があります。
本人としては、ただ見るだけ、話を聞くだけ、感謝を伝えるだけ、のつもりでも、現場は「自分たちの努力が見られている」と感じ、前を向くきっかけにもなるのです。
忙しくてなかなか時間が取れないものではありますが、行くか行かないかで迷うときは、行くことを選ぶ。
ただし、軽く、静かに、丁寧に。そして、得た気づきを次の経営判断に生かす。
この小さな積み重ねが、組織をしなやかに強くしていきます。
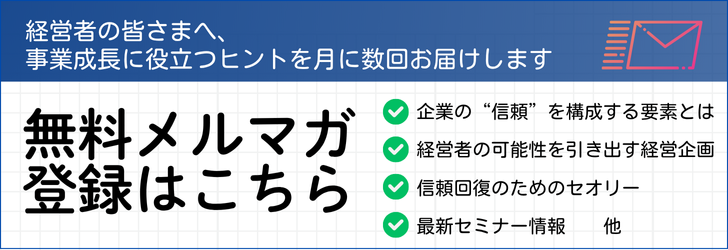
著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

最新刊
企業の信頼を対価に変えて収益性を大きく高める「トラスタライズ」5大ポイント
自社が大切にしてきた「信頼」や、潜在的な無形の価値を、どうすれば大きな対価に変えて収益をあげていくことができるか…。
信頼を対価に変える独自メソッド「トラスタライズ」の手法で企業のこれまでになかった収益の上げ方を提示する専門家が、その具体的なポイントを社長の視点で解説した実用書。

目次
ポイント1:「対価に変えられる信頼」の見つけ方
ポイント2:信頼を効率的に対価に変える戦略の描き方
ポイント3:信頼を可視化・証明する仕組みの作り方
ポイント4:信頼から確実に対価を得るための訴求のやり方
ポイント5:信頼活用に向けた社内の意識改革のやり方
価 格:¥2,200 (税込)
発売元:日本コンサルティング推進機構