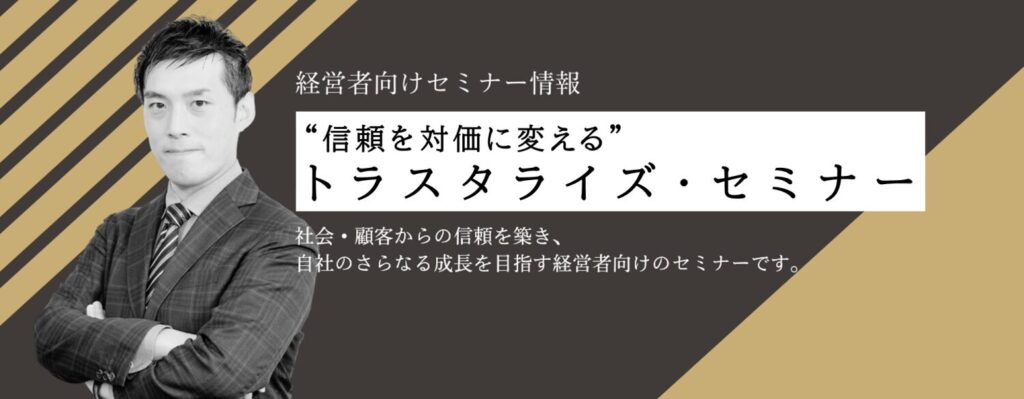第82回 経営者が意識すべき「言語化」とは
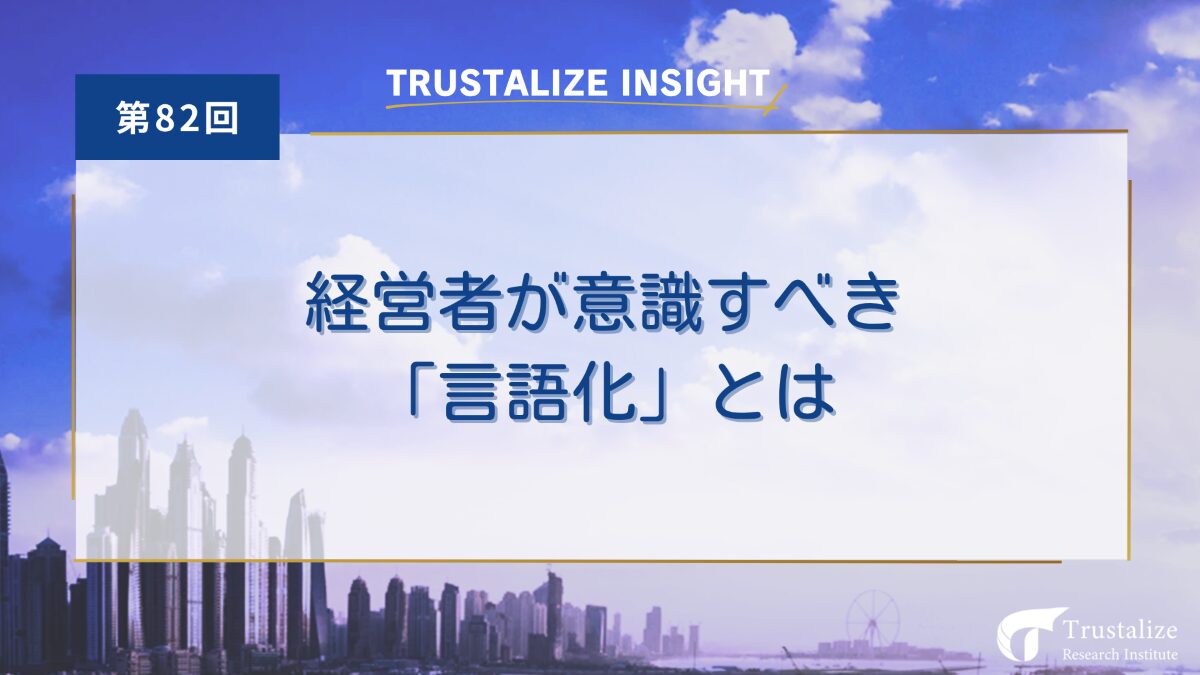
経営者の考えは、言語化されてはじめて力を持ちます。曖昧な表現は組織を迷わせ、明確な言葉はチームを動かす原動力になります。
「池尻さん、数字よりも“言葉”のほうが難しいですね…」
現在、筆者が中期経営計画の策定をお手伝いしているある社長が、ふとつぶやかれました。事業戦略や収支計画を、社内外に伝えるための資料を作成していたときのことです。
「“挑戦”って、うちではどこまでを指すのか?」「“主体性”って、結局どういう行動なのか?」計画の概要が見えてきて、具体性とわかりやすさを付与していこうとするとき、この難題に直面したのです。
経験上、この光景はどの会社でも少なからず起こります。経営者が何か考えを示すうえでは必須のプロセスといえるでしょう。むしろ、この「産みの苦しみ」なくしては、社長の頭の中にある理念や方針は他者から見れば曖昧なままなのです。
経営者が「こういうつもりで伝えた」と思っていても、誰も理解していないということにもなりかねません。今回は、経営者にとっての「言語化の力」について考えてみたいと思います。
なぜ経営者に「言語化力」が求められるのか
企業経営は、意思決定と伝達の連続です。
多くの経営者が日々の意思決定に思考を巡らせますが、いくら優れた判断をしたとて、伝達がうまくいかなければ、現場は意図通りに機能しません。
「なぜ動いてくれないのか」と嘆く前に、そもそも経営者が自らの考えをどれだけ明確な言葉に組織に落とせているかを点検すべきです。
たとえば「お客様第一主義」というスローガンを掲げる会社があるとします。
ある社員は「お客様の要望を、すべて言われたとおりに応えることが第一」と理解し、
別の社員は「言われたこととは異なるとしても、長期的にお客様のためになる提案をすることが第一」と理解していたとします。
この理解のズレは、現場での行動のズレにつながり、価値提供、ブランディングなど多くの面でズレを引き起こしていくのです。
つまり、経営者の言葉が曖昧であるほど、組織の焦点もずれていく。
言語化とは、単なるスローガンづくりではありません。
“何をする会社で、どんな未来を目指し、どんな行動を良しとするのか”を具体的に描き、誰にでも同じ意味で伝わるように整理する作業です。
このプロセスを疎かにすると、社員はバラバラな行動をとったり、社長の意図を忖度しながら働いたりするようになり、意思決定のスピードも、主体的な行動も失われていってしまうのです。
「言葉を整えること」は、実は経営の根幹そのものであるともいえるでしょう。
“わかりやすい言葉”が、組織を動かす
経営者の発する言葉は、社内の“共通認識”を形づくります。
だからこそ、抽象的な表現や小難しい表現ではなく、「誰にでも同じ意味で伝わるわかりやすい言葉」を丁寧に選ぶ必要があります。
このときの「わかりやすさ」には、「解釈の余地を残さない」ということも重要です。単に平易な日本語を使うことではなく、誰が読んでも・聞いても同じ行動に結びつく表現にすることを意味します。「自分の思考を他者に預ける」ことであるともいえるでしょう。
言葉を磨くポイントを3つ挙げるとすれば、次のようになります。
1つ目は、抽象語の中に、なるべく具体的な用語を織り込むこと。
たとえば「挑戦」という言葉を掲げるとき、それが「既存事業の深化」なのか、「○○という新しい事業への参入」なのか、受け手の置かれた状況や役割によって意味は変わります。
「当社にとっての挑戦とは何か」をとにかく具体的に語ることで、社員が同じ方向に進めるようになります。
2つ目は、曖昧な時間軸を明確にすること。
経営者の頭の中には中長期の絵がありますが、社員の多くは「今月・今期」に視点が寄っています。この時間軸の違いは、組織の間にズレを生むことが少なくありません。“いつまでに、どんな状態を目指すのか”を明示することが、行動の優先順位を整えます。
3つ目は、表現の細部にこだわること。
同じ内容でも、言葉の選び方や語順ひとつで受け手の印象は大きく変わります。たとえば「地域ナンバーワンのお客様価値創造企業」というスローガンの場合、お客様価値が地域で最も優れているのか、お客様価値を高めた結果シェアなどで地域ナンバーワンの地位を築くのか、受け手によって解釈が分かれる可能性があります。
このような解釈の違いを生み出しかねない表現を避けるよう、経営者が言葉の細部まで意識を向けることで、伝えるべき内容そのものも磨かれ、メッセージの精度が格段に上がるのです。
これらを意識し、実践している会社ほど、組織の意思統一が図られ一枚岩になっていきます。逆に言えば、伝わる言葉の精度で、組織の一体感は左右されるのです。
言葉を磨くには、他者との対話が欠かせない
ただし、自分の言葉を自分だけで磨くことはなかなか困難です。
経営者本人が「これで十分伝わるだろう」と思っていても、受け手の理解は往々にして違います。だからこそ、他者との対話の中で客観性を担保することが必要です。
筆者がご支援を行う際も、“言葉の壁打ち”には多くの時間とエネルギーを注ぎます。社長に理念や戦略を、どんな表現でもいいのでまずは語って頂く、そして社外の人間である筆者が「それは○○という表現だとどうでしょうか?」と掘り下げていく。一筋縄ではいかないこともありますが、やり取りを続けていくと、社長ご自身が「ああ、自分が言いたいのはこういうことだったのか」と気づかれる瞬間が必ずあります。
言語化とは、思考を外に出し、他者の視点で整えるプロセスであるともいえるでしょう。率直な議論ができるのであれば、社内の方でも問題ありません。経営者の頭の中の“もやもや”を整理し、組織に伝わる形に翻訳するためには、まずは一旦外に出して、他の人に意見をもらうのが有効です。
経営者が言語化を怠ると、組織は迷います。
一方、明確な言葉をもって意思を伝えるリーダーのもとでは、社員が安心して動き出すことができます。その違いが、経営の成果に直結することは言うまでもありません。
また、今後はAIを使いこなしていかなければならない時代でもあります。
AIに正確に意図を伝えるにも、やはり“明確な言葉”は必要です。
曖昧なままでは正しく動けないのは、AIも人も同じです。
経営とは、言葉と論理で未来を描き、伝える営みという側面を持ちます。
社内に相談相手がいなければ、外部の専門家と対話しながらでも、ぜひ言葉を磨いてください。あなたの言葉が変われば、組織の明日もきっと変わっていくでしょう。
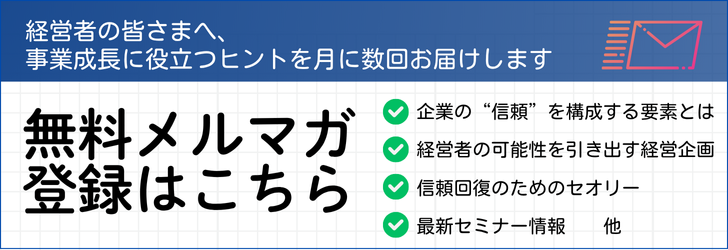
著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

最新刊
企業の信頼を対価に変えて収益性を大きく高める「トラスタライズ」5大ポイント
自社が大切にしてきた「信頼」や、潜在的な無形の価値を、どうすれば大きな対価に変えて収益をあげていくことができるか…。
信頼を対価に変える独自メソッド「トラスタライズ」の手法で企業のこれまでになかった収益の上げ方を提示する専門家が、その具体的なポイントを社長の視点で解説した実用書。

目次
ポイント1:「対価に変えられる信頼」の見つけ方
ポイント2:信頼を効率的に対価に変える戦略の描き方
ポイント3:信頼を可視化・証明する仕組みの作り方
ポイント4:信頼から確実に対価を得るための訴求のやり方
ポイント5:信頼活用に向けた社内の意識改革のやり方
価 格:¥2,200 (税込)
発売元:日本コンサルティング推進機構