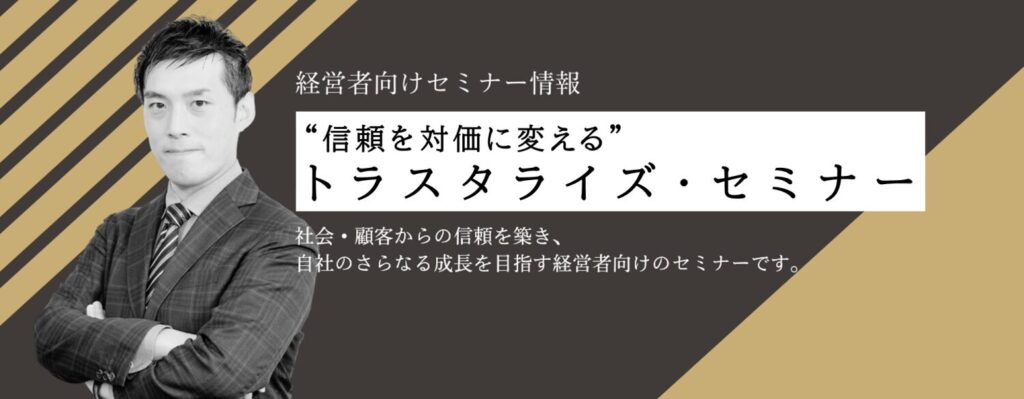第84回 自社の強み、本当にわかっていますか?
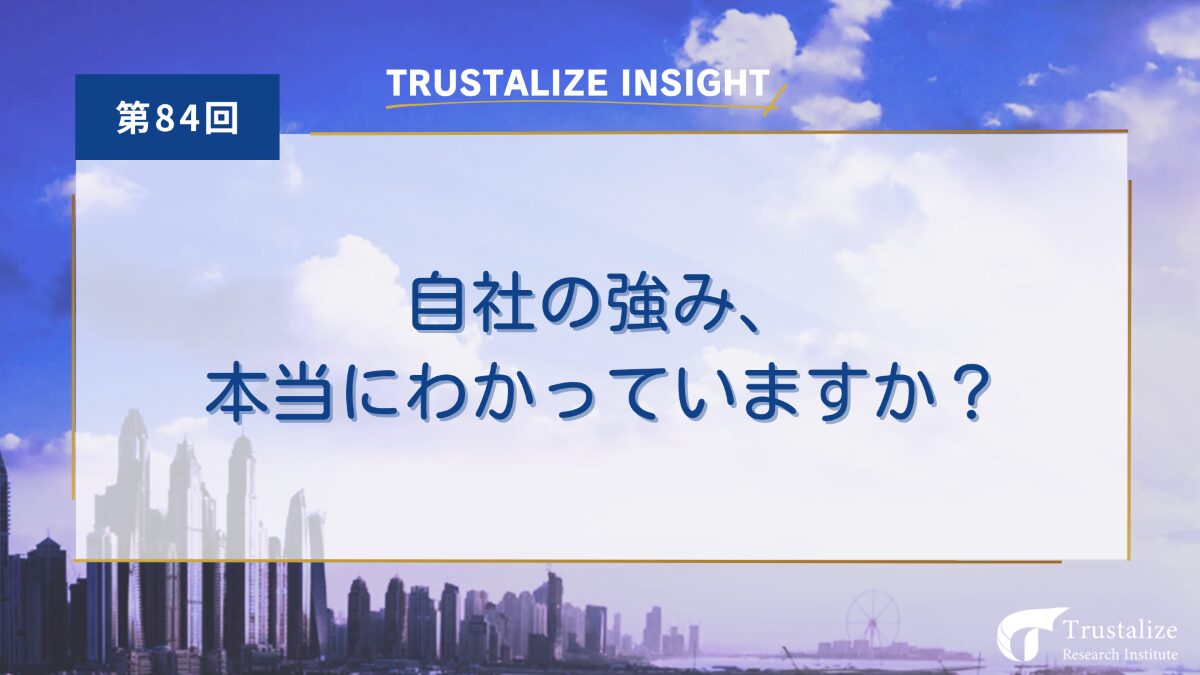
中小企業の「本当の強み」は、顧客に選ばれる理由をつくる要素。その見極めには、現場・顧客の声を集めて認識を揃え、焦点を絞り込むことが必要不可欠です。
「そう考えると、うちの強みは製品力というよりは、小回りの良さや柔軟な生産体制なのかもしれませんね……」
先日、千葉県にある当社クライアントのK社様(製造業)にお伺いして、経営計画の作りこみをお手伝いしていた際、社長がおっしゃった一言です。「貴社の本当の強みは何だと思いますか?」という問いかけから始まり、色々とお伺いするなかで出てきた答えでした。
中小企業は「強みに集中すべきだ」とよく言われます。いわゆるSWOT分析など、経営学のフレームワークでも基本となる概念です。しかし実際には、自社の「本当の強み」を正しく認識できていないケースも少なくありません。
今回は、自社にとっての「強み」を正しく捉え、もう一歩深く掘り下げるための視点について取り上げます。
製品力・サービス力は本当に「強み」なのか?
「うちの強みは製品そのものだ」「サービスの質だ」
自社の強みについて、こう捉える経営者は多くいらっしゃいます。もちろん、それが絶対に間違いというわけではなく、圧倒的な製品・サービス力で売り上げにつなげる会社も存在するでしょう。
しかし、実際に詳しく話を聞いて掘り下げていくと、「製品力こそが強み」という認識が必ずしも正確ではない場合もあります。
一般的に、中小企業の「強み」を想像してみると、「職人の技」のように量は増やせないが高い技術で「圧倒的品質」を実現している、というようなイメージをしがちです。
しかし、中小企業の現実として、
- 設備や研究開発では大手に勝ちづらい
- 消費者も、微細な品質差にそこまで敏感ではない
- 競争軸そのものも、製品・サービスの質だけではない
といった状況も少なくありません。実は、製品・サービスの質そのものは「前提条件」にすぎず、選ばれる理由の中核は別のところに存在することもあるのです。
「選ばれる理由」こそが強みである
では、強みとは何なのか。
筆者が重視しているのは、
「自社の本当の強みとは、顧客が”あなたの会社を選ぶ理由”と直接対になる能力である」
という視点です。
極端に言えば、いくら自社が「これが強みだ」と思っていても、顧客の購買行動に影響していなければそれは強みではありません。
たとえば、
- 「どこよりも低価格」を実現するための、安価に調達できる仕組みや生産性
- 「いつでもすぐ対応してくれる」という安心感や対応スピード
- 「気持ちの良いサービス体験」を支える担当者の誠実さや接客態度
カッコの中が選ばれる理由であり、そのあとにつながるのが強み、ということになります。
冒頭の会社でも、社長は当初は「製品力が強みだ」と考えていました。しかし、自社がなぜ受注を獲得できているのか、という問いに対し、実際に現場の声を聞いて整理していくと、
- 一定品質の製品を、
- 必要なタイミングに、
- 少ロットでも柔軟に供給できる
この、顧客から見た「小回りの良さ」こそが、最も評価されているポイントでした。そしてそれは、この会社独自の、柔軟に調整できる生産システムと外注管理の仕組みだったのです。議論を経て、これこそが強みである、ということが明確になり、冒頭の社長のご発言が生まれたのでした。
「本当の強み」の見つけ方と留意点
強みを正しく捉えるには、「現場の声」と「顧客の声」を、力を入れて意図的に拾うことが欠かせません。
最もオーソドックスなやり方は、顧客と日々接している営業担当者に聞くことです。もちろん、直接顧客に聞ける場合はそれでも問題ありません。
- なぜ自社の商品・サービスが選ばれているのか
- 他社と比較された時、最終的に自社を選ぶ理由は何か
- 自社の価値を語るとき、どのポイントで反応が変わるか
こうした情報は、社長が現場を離れている期間が長かったりすると、社長自身も正しく認識・理解できていないことがあります。さらに、営業担当者同士でも認識が異なることも少なくありません。
こうした場合には、自社として最も重視すべき要素を1つか2つ程度に絞り込むことが大切です。
なぜなら、「選ばれる理由」を磨き上げることが、中長期的な経営の指針の1つになることが多いです。しかし、リソースの限られる中小企業の場合、あまり多くの要素を伸ばすことが難しいからです。
色々な要素に手を出して焦点がボヤけてしまえば、投資も人材配置も分散し、メッセージも統一されなくなります。
まずは社内の意見を集め、
「自社は何によって選ばれているのか」
その認識を揃えることが、強みの深堀りの第一歩です。
自社にとっての「強み」とは、顧客があなたの会社を選ぶ理由を形づくるものといえます。
つまり、「強み」明確にするということは、
「何にこだわり、どのようにして選ばれるのか」
という、自社が提供すべき価値の焦点を定めることともいえます。
強みが明確になると、
- その企業が顧客に対してどんな価値を生み出すのか
- その結果、社会にどのような貢献を果たせるのか
- それらの成果を最大化するために、どのような能力を高めていくのか
こうした議論も自然と輪郭を帯びてきます。
「なんとなくイメージで決める」のではなく、「選ばれる理由としての強み」を具体的に定義し、磨いていくことで、企業の発信・事業の成長・価値の創造は、驚くほど一貫性を持ち始めます。そしてこれが自社の信頼・ブランド構築を加速させる第一歩にもなります。
それでは、あなたの会社の「本当の強み」は何でしょうか。ぜひ、もう一段深く掘り下げてみてください。
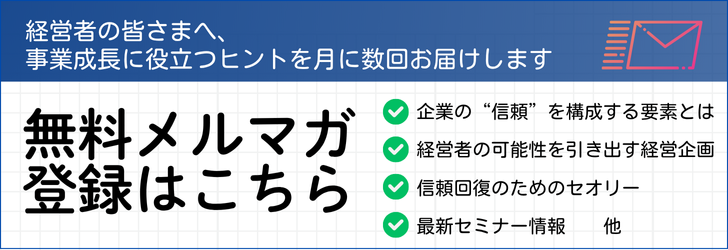
著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

著者プロフィール
トラスタライズ総研株式会社
代表取締役 池尻直人
社外経営企画室長・経営企画パートナー。
独自の「トラスタライズ手法」を用いて、見えない信用や信頼を、目に見えるカタチに変え、対価へと変えることで多くの経営者から注目を集めている。企業経営において社会・顧客双方の価値の創出が求められる時代にあって、顧客企業が持続的に成長し、信頼を築き上げていけるよう、経営企画機能を伴走型で提供している。

最新刊
企業の信頼を対価に変えて収益性を大きく高める「トラスタライズ」5大ポイント
自社が大切にしてきた「信頼」や、潜在的な無形の価値を、どうすれば大きな対価に変えて収益をあげていくことができるか…。
信頼を対価に変える独自メソッド「トラスタライズ」の手法で企業のこれまでになかった収益の上げ方を提示する専門家が、その具体的なポイントを社長の視点で解説した実用書。

目次
ポイント1:「対価に変えられる信頼」の見つけ方
ポイント2:信頼を効率的に対価に変える戦略の描き方
ポイント3:信頼を可視化・証明する仕組みの作り方
ポイント4:信頼から確実に対価を得るための訴求のやり方
ポイント5:信頼活用に向けた社内の意識改革のやり方
価 格:¥2,200 (税込)
発売元:日本コンサルティング推進機構